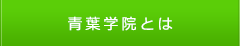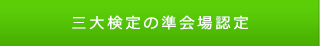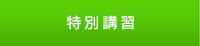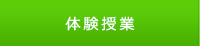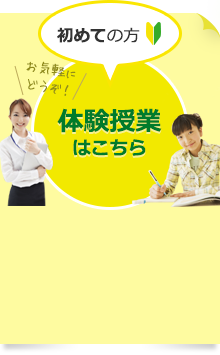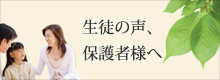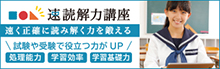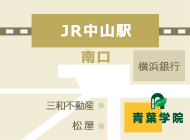“自分でできる”を増やす家庭学習の仕組みづくり
— 家で“自分から動ける子”はどう育つ?
🏠 家での勉強、うまくいっていますか?
「やりなさいと言わないとやらない」
「机に向かっても集中が続かない」
こんな悩み、どこのご家庭でもよくあります。
でも実は、
**“やる気”ではなく、“仕組みがあるかどうか”**が分かれ道なんです。
家庭学習をうまくいかせるコツは、
自主性が生まれる“環境づくり”にあります。
🧩 自分で動ける子の家には、共通点がある
青葉学院で見ていると、
「家でも自分で進められる子」にはいくつかの共通点があります👇
✔ ① 勉強を始める“きっかけ”が決まっている
帰宅したら制服を脱ぐ → 5分だけ机に座る
夕食前に1科目
風呂前に英単語5個
ポイントは、
「時間」ではなく“行動”に結びつけること。
行動にセットすると、習慣化しやすくなります。
✔ ② 机の周りに“余計なものがない”
スマホ、マンガ、お菓子、ゲーム機…
誘惑があると、どんな中学生も無理です。
逆に、
「教材だけある」環境を作ると、集中しやすくなります。
これは大人でも同じですよね。
✔ ③ 勉強量が“ちょっと少ない”
え?少ないの?と思うかもしれません。
でも、家庭学習のコツは
**「毎日できる量にすること」**です。
プリント1枚
英単語5個
漢字3つ
ワーク1ページの半分
このくらいだと“続けられる自信”が積み上がり、
結果的に学力がつきます。
🪴 家庭学習は「仕組み」が育てる
家庭学習で伸びる子のポイントは、
やらせる → やれるようになる → 自分でやる
この流れが自然に作られていること。
そのために青葉学院では、
以下のような“仕組み”を家庭でも提案しています👇
🔧 家でできる「仕組み」例
❇ 学校のワークは“先に少し進めておく”
❇ 英単語はスマホではなく紙で5分
❇ ワークは“やる場所を固定”する
❇ できたらシール or チェックで“見える達成感”を作る
❇ 夜は翌日の準備を必ず10分だけ
家庭でも実践できる、小さな仕組みを積み重ねるだけで
自主性は自然と育っていきます。
🌱 青葉学院の考え方
家庭学習の目的は、
「長時間やること」でも、
「たくさん終わらせること」でもありません。
“自分でできる”という感覚を増やしていくこと。
これが育つと、
勉強に自信がつく
自分で進められる
テスト前の準備が早くなる
と、良い循環が生まれます。
青葉学院は、
家庭と塾がいっしょに“学びの根っこ”を育てることを大切にしています。
- HOME
- 新着情報
- 2025/12/10
- 🌿勉強習慣の“根っこ”を育てる【第5回】
- 2025/12/02
- 🌿勉強習慣の“根っこ”を育てる【第4回】
第4回:「間違えた問題こそ宝物」
—“間違い直し”で学力が伸びる理由とは?
❌ 間違える=ダメじゃない
多くの中学生が思っています。
「間違えるのは恥ずかしい」
「できない自分を見たくない…」
でもその考え、すごくもったいないんです。
なぜなら、
正解できた問題には、もう伸びしろはない
から。
本当に成績を上げてくれるのは、
できなかった問題です。
🔍「なぜ間違えたか」を見つけると、一気に伸びる
間違い直しをするときは、
ただ答えを赤で書き直すのではなく👇
✔ どこでつまずいた?
計算ミス?
解き方を忘れていた?
問題文を読み違えた?
✔ 次どうすればできる?
注意点を書く
解き方のメモを足す
似た問題をもう1問やる
間違えた原因を“名前”にしてあげると、
次は避けやすくなります。
📌 点数が上がる子は、ここが違う!
青葉学院の生徒を見ていて感じること。
成績が伸びる子は
「間違いを集めている」
間違いノートを作る
同じミスはすぐ対策
テスト前は“間違いリスト”で最終確認
この3つがあると、
点数は安定して伸びていきます。
💡「間違えるほど賢くなる」
間違いは、失敗ではなく
学びの証です。
次の成長のヒント
苦手克服の入り口
成績アップの最短ルート
全部、間違えた問題が持っています。
だから、青葉学院では
**間違い直しを“宝探し”**だと考えています✨
🌱 青葉学院の考え方
勉強の本当の目的は、
「正解すること」ではなく
**「できる自分に変わっていくこと」**です。
そのために
間違いを恐れず、
前向きに向き合う力を伸ばしていきます。
一緒に、宝物をたくさん見つけていきましょう。
—“間違い直し”で学力が伸びる理由とは?
❌ 間違える=ダメじゃない
多くの中学生が思っています。
「間違えるのは恥ずかしい」
「できない自分を見たくない…」
でもその考え、すごくもったいないんです。
なぜなら、
正解できた問題には、もう伸びしろはない
から。
本当に成績を上げてくれるのは、
できなかった問題です。
🔍「なぜ間違えたか」を見つけると、一気に伸びる
間違い直しをするときは、
ただ答えを赤で書き直すのではなく👇
✔ どこでつまずいた?
計算ミス?
解き方を忘れていた?
問題文を読み違えた?
✔ 次どうすればできる?
注意点を書く
解き方のメモを足す
似た問題をもう1問やる
間違えた原因を“名前”にしてあげると、
次は避けやすくなります。
📌 点数が上がる子は、ここが違う!
青葉学院の生徒を見ていて感じること。
成績が伸びる子は
「間違いを集めている」
間違いノートを作る
同じミスはすぐ対策
テスト前は“間違いリスト”で最終確認
この3つがあると、
点数は安定して伸びていきます。
💡「間違えるほど賢くなる」
間違いは、失敗ではなく
学びの証です。
次の成長のヒント
苦手克服の入り口
成績アップの最短ルート
全部、間違えた問題が持っています。
だから、青葉学院では
**間違い直しを“宝探し”**だと考えています✨
🌱 青葉学院の考え方
勉強の本当の目的は、
「正解すること」ではなく
**「できる自分に変わっていくこと」**です。
そのために
間違いを恐れず、
前向きに向き合う力を伸ばしていきます。
一緒に、宝物をたくさん見つけていきましょう。
- 2025/11/25
- 🌿勉強習慣の“根っこ”を育てる【第3回】
🌿第3回:「覚えられない」は努力不足じゃない
— 記憶の仕組みを味方にする“忘れにくい勉強”とは?
😥「頑張っているのに覚えられない…」
そんな声、中学生から本当によく聞きます。
でも実は、
覚えられない=努力が足りない
ではありません。
“覚え方を知らないだけ”のことが多いんです。
だからこそ、青葉学院では
「記憶の仕組み」を使った勉強法
を大切にしています。
🧠 記憶のカギは「時間」と「回数」
脳は、
「何度も出会った情報」を大事なものと判断して残します。
つまり、
一気に覚えるより、短い時間を何度もが最強の覚え方。
たとえば👇
15分×1回 → すぐ忘れる
5分×3回 → 記憶に残りやすい
同じ15分でも、分けて行うほうが圧倒的に効果があります。
📅 “忘れる前にちょっと復習”がポイント
忘れる前に復習することで、記憶が強くなります。
青葉学院では、生徒にこの3つを意識してもらっています👇
✔ ① 翌日までにもう一度
記憶は24時間でかなり薄くなります。
その前に“ちょっと復習”するだけで全然違います。
✔ ② 3日後にももう一回
ここでの復習が定着の分かれ道。
「3日後ルール」を作っておくと、習慣になります。
✔ ③ テスト前に仕上げの総復習
この段階では「新しく覚える」ではなく、
“忘れていたものを戻す”作業になります。
📚 ノートより「声に出す」「見ないで書く」の方が効く
覚えるとき、
ただ見ているだけでは脳は動きません。
一番記憶に残るのは👇
声に出す(五感を使う)
見ないで書く(脳が情報を探す)
説明してみる(理解が深まる)
青葉学院でも、英単語・理科・社会で
「5秒だけ見て→閉じて書く」練習をよく行います。
これ、シンプルなのに本当に効果絶大です。
🌱 青葉学院の考え方
青葉学院では、子どもたちに
結果より方法を変えることで、覚える力は伸ばせる
ということを実感してほしいと考えています。
「覚えられない」
「忘れちゃう」
は、ただの“脳の仕組み”です。
責める必要はまったくありません。
正しいやり方を知れば、誰でも確実に伸びていきます。
— 記憶の仕組みを味方にする“忘れにくい勉強”とは?
😥「頑張っているのに覚えられない…」
そんな声、中学生から本当によく聞きます。
でも実は、
覚えられない=努力が足りない
ではありません。
“覚え方を知らないだけ”のことが多いんです。
だからこそ、青葉学院では
「記憶の仕組み」を使った勉強法
を大切にしています。
🧠 記憶のカギは「時間」と「回数」
脳は、
「何度も出会った情報」を大事なものと判断して残します。
つまり、
一気に覚えるより、短い時間を何度もが最強の覚え方。
たとえば👇
15分×1回 → すぐ忘れる
5分×3回 → 記憶に残りやすい
同じ15分でも、分けて行うほうが圧倒的に効果があります。
📅 “忘れる前にちょっと復習”がポイント
忘れる前に復習することで、記憶が強くなります。
青葉学院では、生徒にこの3つを意識してもらっています👇
✔ ① 翌日までにもう一度
記憶は24時間でかなり薄くなります。
その前に“ちょっと復習”するだけで全然違います。
✔ ② 3日後にももう一回
ここでの復習が定着の分かれ道。
「3日後ルール」を作っておくと、習慣になります。
✔ ③ テスト前に仕上げの総復習
この段階では「新しく覚える」ではなく、
“忘れていたものを戻す”作業になります。
📚 ノートより「声に出す」「見ないで書く」の方が効く
覚えるとき、
ただ見ているだけでは脳は動きません。
一番記憶に残るのは👇
声に出す(五感を使う)
見ないで書く(脳が情報を探す)
説明してみる(理解が深まる)
青葉学院でも、英単語・理科・社会で
「5秒だけ見て→閉じて書く」練習をよく行います。
これ、シンプルなのに本当に効果絶大です。
🌱 青葉学院の考え方
青葉学院では、子どもたちに
結果より方法を変えることで、覚える力は伸ばせる
ということを実感してほしいと考えています。
「覚えられない」
「忘れちゃう」
は、ただの“脳の仕組み”です。
責める必要はまったくありません。
正しいやり方を知れば、誰でも確実に伸びていきます。
- 2025/11/18
- 🌿勉強習慣の“根っこ”を育てる【第2回】
第2回:「ノートを“書くため”から“考えるため”へ」
—「きれい」より「伝わる」「わかる」ノートとは?
✏️ ノートがきれい=学力が高い、ではない?
小学生のころは「ていねいに書く」が重視されがちですが、
中学生になると、“見た目のきれいさ=成績”ではありません。
むしろ、
「そのノートで自分の頭は動いているか」
が大切になってきます。
青葉学院にも、
字が美しくて整っているのにテストになると点が伸びない子
字は多少ラフでも、要点がまとまっていて理解が深い子
がいます。
違いは、“書く目的”の違いです。
🧠 ノートは「思考の作業台」
ノートを取る目的は、
先生の話を写すことではなく、考えるための材料を残すこと。
具体的にはこんな工夫が効果的👇
✔ ① 重要語句は「囲む」「矢印でつなぐ」
視覚的に強弱をつけると、後から見返すときに理解が早くなります。
✔ ② 自分の言葉でひとことまとめを書く
「つまり〜」「ここは○○と同じ意味」
という一文を加えるだけで、理解度が大きく変わります。
✔ ③ 問題を解いたら“どこでつまずいたか”を書く
間違いを「赤で書き直すだけ」では、同じところで躓きます。
ポイントは、
「なぜ間違えたか」「次どうするか」を短く書くこと。
これだけで、“復習の質”が一段上がります。
🏡 青葉学院が大切にしていること
青葉学院は、
書くことに時間をかけすぎないノート作り
を大切にしています。
理由はひとつ。
ノートは「作品」ではなく「思考の道具」だからです。
きれいに仕上げようとすると、
授業中に考える余裕がなくなる
復習するときに“どこが大事なのか”見えなくなる
といったデメリットもあります。
だからこそ、
“整えるより、わかる”ノート
を目指しています。
🌱 「頭が動くノート」は、学力の根っこになる
考えながら書く習慣は、
・理解力
・読解力
・自分で説明する力
につながっていきます。
ノートは「学力の根っこ」を育てる、とても大切な場所です。
少しずつで良いので、今日からノートを“考える道具”にしていきましょう。
—「きれい」より「伝わる」「わかる」ノートとは?
✏️ ノートがきれい=学力が高い、ではない?
小学生のころは「ていねいに書く」が重視されがちですが、
中学生になると、“見た目のきれいさ=成績”ではありません。
むしろ、
「そのノートで自分の頭は動いているか」
が大切になってきます。
青葉学院にも、
字が美しくて整っているのにテストになると点が伸びない子
字は多少ラフでも、要点がまとまっていて理解が深い子
がいます。
違いは、“書く目的”の違いです。
🧠 ノートは「思考の作業台」
ノートを取る目的は、
先生の話を写すことではなく、考えるための材料を残すこと。
具体的にはこんな工夫が効果的👇
✔ ① 重要語句は「囲む」「矢印でつなぐ」
視覚的に強弱をつけると、後から見返すときに理解が早くなります。
✔ ② 自分の言葉でひとことまとめを書く
「つまり〜」「ここは○○と同じ意味」
という一文を加えるだけで、理解度が大きく変わります。
✔ ③ 問題を解いたら“どこでつまずいたか”を書く
間違いを「赤で書き直すだけ」では、同じところで躓きます。
ポイントは、
「なぜ間違えたか」「次どうするか」を短く書くこと。
これだけで、“復習の質”が一段上がります。
🏡 青葉学院が大切にしていること
青葉学院は、
書くことに時間をかけすぎないノート作り
を大切にしています。
理由はひとつ。
ノートは「作品」ではなく「思考の道具」だからです。
きれいに仕上げようとすると、
授業中に考える余裕がなくなる
復習するときに“どこが大事なのか”見えなくなる
といったデメリットもあります。
だからこそ、
“整えるより、わかる”ノート
を目指しています。
🌱 「頭が動くノート」は、学力の根っこになる
考えながら書く習慣は、
・理解力
・読解力
・自分で説明する力
につながっていきます。
ノートは「学力の根っこ」を育てる、とても大切な場所です。
少しずつで良いので、今日からノートを“考える道具”にしていきましょう。